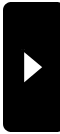2009年12月26日
中小企業金融円滑化法
12月4日に施行された「中小企業金融円滑化法」。
中小企業庁のホームページにも紹介があります。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/index.htm
実際の対応は、融資を受けている金融機関に確認するのが一番のようです。
中小企業庁のホームページにも紹介があります。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/index.htm
実際の対応は、融資を受けている金融機関に確認するのが一番のようです。
2009年11月25日
役員借入金のある会社
会社の資金繰りの都合上、会社にお金がない場合、役員から借入をする場合があります。
通常、会社は赤字か税務上の繰越欠損をかかえている場合が多いです。
このような状況にあるときは、役員報酬をガタッと減額し、生活費は役員借入の返済金でまわしていけば、決算書の見場はよくなります。
また、役員報酬は減るので、個人(役員)の源泉所得税は少なくなり、また社会保険料も少なくなり、個人(役員)の手取りはアップします。
難点は、年収がガタッと少なくなるので、子供がアパートを借りる時等に親の保証を兼ねて源泉徴収票の提出を求められた時にあまりに年収が少ないと保証できない場合があります。
一長一短ですが、役員借入金が多い会社については、役員報酬の減額を考えてみるのもいいかと思います。
通常、会社は赤字か税務上の繰越欠損をかかえている場合が多いです。
このような状況にあるときは、役員報酬をガタッと減額し、生活費は役員借入の返済金でまわしていけば、決算書の見場はよくなります。
また、役員報酬は減るので、個人(役員)の源泉所得税は少なくなり、また社会保険料も少なくなり、個人(役員)の手取りはアップします。
難点は、年収がガタッと少なくなるので、子供がアパートを借りる時等に親の保証を兼ねて源泉徴収票の提出を求められた時にあまりに年収が少ないと保証できない場合があります。
一長一短ですが、役員借入金が多い会社については、役員報酬の減額を考えてみるのもいいかと思います。
2009年11月24日
図で考える
損益計算書は、経費を固定費と変動費とに分けた「変動損益計算書」に組み替えると、「経営安全率」等が算出でき、便利です。
それでも理解できない方には、下記のようなストラック表を使って、会社の状況を理解してもらうことがあります。
--------------|
| 売上 | 変動費 |
| |-------- |
| | 限界 | 固定費 |
| | 利益 |----|
| | | 利益 |
--------------
具体的な使い方は、ストラック表で検索してみて下さい。
それでも理解できない方には、下記のようなストラック表を使って、会社の状況を理解してもらうことがあります。
--------------|
| 売上 | 変動費 |
| |-------- |
| | 限界 | 固定費 |
| | 利益 |----|
| | | 利益 |
--------------
具体的な使い方は、ストラック表で検索してみて下さい。
2009年11月20日
資金繰り表
お金は入って出ていきます。
入る方が多ければお金が貯まり、出ていく方が多ければお金が減っていきます。
どんどん出ていくとお金は底をつくので、事業をやめるか、お金がもっと入るよう売上を伸ばすか、お金の出を少なくするよう経費削減に努めるかのどれか(ないしそれらを組み合わせて)を選択しなくてはなりません。
あまり考えないで、とりあえずお金の入りを増やすために、金融機関から借入を行い、お金を増やすこともできます。
金融機関によっては、借入時に「資金繰り表」を提出して下さい、と言われることがあります。
頭の中、ないしは電卓をたたいて、お金の出と入りを管理している会社に、「資金繰り表」の提出と言われると、どうして作成していいものか、悩むことになります。
資金繰り表に関する市販の本もたくさん出版されていますが、資金繰り表のフォームも多く、どれが自社に最適か、またまた悩んだりしてしまいます。
資金繰りも大変ですが、資金繰り表の作成も、中小企業には大変のようです。
会計事務所は、資金繰り表の作成のお手伝いをしている場合も多いので、作成に困ったら、担当者に聞いてみましょう。
入る方が多ければお金が貯まり、出ていく方が多ければお金が減っていきます。
どんどん出ていくとお金は底をつくので、事業をやめるか、お金がもっと入るよう売上を伸ばすか、お金の出を少なくするよう経費削減に努めるかのどれか(ないしそれらを組み合わせて)を選択しなくてはなりません。
あまり考えないで、とりあえずお金の入りを増やすために、金融機関から借入を行い、お金を増やすこともできます。
金融機関によっては、借入時に「資金繰り表」を提出して下さい、と言われることがあります。
頭の中、ないしは電卓をたたいて、お金の出と入りを管理している会社に、「資金繰り表」の提出と言われると、どうして作成していいものか、悩むことになります。
資金繰り表に関する市販の本もたくさん出版されていますが、資金繰り表のフォームも多く、どれが自社に最適か、またまた悩んだりしてしまいます。
資金繰りも大変ですが、資金繰り表の作成も、中小企業には大変のようです。
会計事務所は、資金繰り表の作成のお手伝いをしている場合も多いので、作成に困ったら、担当者に聞いてみましょう。
タグ :資金繰り表
2009年11月01日
【問題】税引前利益はいくら?
銀行とお話をしていた経営者。
(銀行)「今の経営状態では、銀行からの借入を順調に返済することができないので、次年度の事業計画では、利益(税引後利益)を700万円あげるくらいにして下さい」
(経営者)「わかりました。そのようになるよう事業計画書を作ってみます」
銀行の方が帰った後、事業計画書を作成し始めた経営者。700万円の利益をあげるには税金も払わないといけないから税金を払う前の利益(「税引前利益」といいます)を計算しないといけないな、と思いました。
そこで顧問税理士に税率を聞くと、30%という返事が返ってきました。
【問題】(税引後)利益700万円をあげるには、税率が30%の時、税引前利益をいくらあげることが必要でしょうか?(解答は明日・・・)
(銀行)「今の経営状態では、銀行からの借入を順調に返済することができないので、次年度の事業計画では、利益(税引後利益)を700万円あげるくらいにして下さい」
(経営者)「わかりました。そのようになるよう事業計画書を作ってみます」
銀行の方が帰った後、事業計画書を作成し始めた経営者。700万円の利益をあげるには税金も払わないといけないから税金を払う前の利益(「税引前利益」といいます)を計算しないといけないな、と思いました。
そこで顧問税理士に税率を聞くと、30%という返事が返ってきました。
【問題】(税引後)利益700万円をあげるには、税率が30%の時、税引前利益をいくらあげることが必要でしょうか?(解答は明日・・・)
タグ :税引前利益